見る・聞く・読む
教育普及 現代の眼 オンライン版 「想いをぎゅっと やきものワークショップ」開催レポート
戻る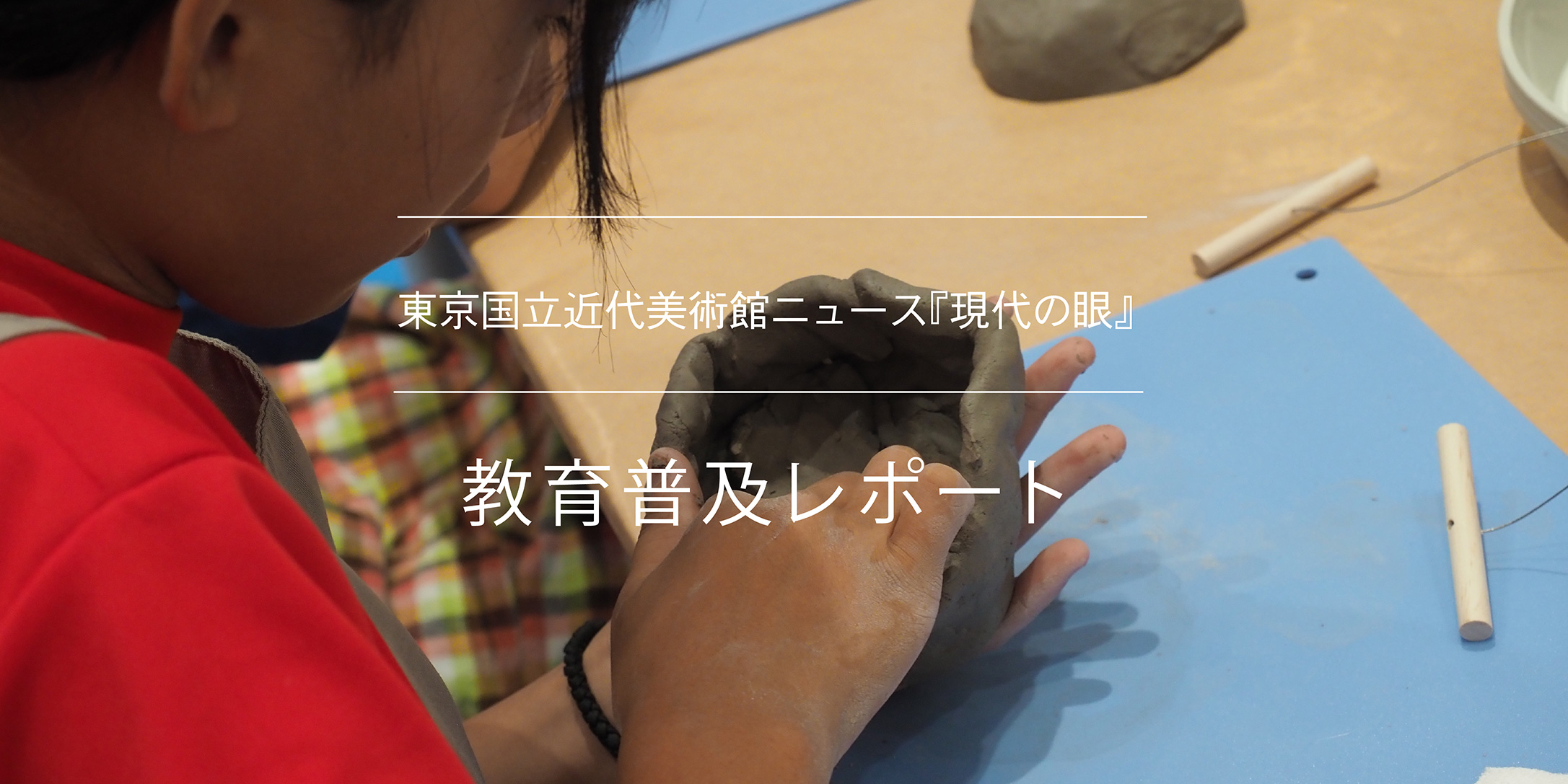
開催日時:2025年8月10日(日)10:00~12:30/会場:国立工芸館多目的室/対象:小学生32名
講師:十一代大樋長左衛門氏(https://ohichozaemon.com/)
主催:国立工芸館、国立アートリサーチセンター/協賛:株式会社スタイリングライフ・ホールディングス プラザスタイル カンパニー/特別協力:大樋美術館

1970年にフランスで絵本が登場して以来、どんなかたちにも変身できるキャラクターとして親しまれてきたバーバパパは今年で55周年。そして国立工芸館も東京から移転開館して10月で5周年を迎えます。この2つを記念した今回の企画は、独立行政法人国立美術館の一番新しい仲間、国立アートリサーチセンターの社会連携促進グループの働きかけで始動しました。
「バーバパパと工芸?」――意外な組み合わせのようですが、バーバパパを観察すると姿かたちには回転体の雰囲気があり、平面なのに手指に架空のテクスチャーが訴えてきます。単独で完成された魅力を放ちながら、個性的なファミリーが揃えば、どんな組み合わせでもばっちり決まる独特の存在感もある。これもまた単体での賞玩に留まらず、複数のオブジェクトで食卓や室内空間の設えを検討してきた工芸文化との親和性を示します。そして多様性やSDGsの意識の先駆けとも読めるストーリー。工芸との共通項が次々と浮かぶなか、バーバパパのしなやかボディ同様に、可塑性の高い陶土に触れる体験が子どもたちの感性を豊かに育むことを期待して、陶芸のワークショップを開催する運びとなりました。講師は春先に日本藝術院会員に就任した陶芸家の十一代大樋長左衛門氏。金沢を代表する焼きものである大樋焼の伝統とグローバルな視野をあわせ持つ氏の言葉は、子どもたちにどのように響くでしょうか。
ワークショップの冒頭、大樋氏が子どもたちに紹介したのは、バーバパパが誕生したときのエピソードでした。地中で種が膨らみ、芽吹くように生まれ出たバーバパパ。焼きものとは「土繋がり」の関係にあることが知らされました。さらに土は木に養分を与え、木の葉はやがて土へと還る自然のサイクルを例に、地球上のすべての物事が誰か/何かとの結びつきを持つのだと話が続きます。「工作ができる」「粘土にさわれる」楽しみや「バーバパパが好き」で来場した子どもたちの顔に、そうしたこととはまた違った、もやもやとしながらもう少しでかたちになりそうな「何か」が浮かんできました。
ここで1点目のチャレンジ、茶わんづくりのデモンストレーションです。球形の土を手にした大樋氏が土を叩くと、みるみるうちに内部構造を抱いたボウル型が現れました。さぁ、いよいよ!と高まる気持ちを制して講師から「その前に」の声。父母からさかのぼる代々の想いを繋ぐ代表として、今、私たちは目の前に置かれた土に触れようとしていることを意識したい。そのために「目を瞑り、大切な誰かを想う」時間が設けられました。

目を開き、あらためて土に手を遣る姿は最前の摑みかかるかのごときとは大違い。研ぎ澄まされた五感が手と土の鳴る音、土に見る手痕へと向かって開きます。どの子も幾らか神妙で、そしてすごく真剣。しかし「ペチペチ」と立てるリズムにやがて笑顔もほころんで、参加者の心情が剛柔絶妙のバランスで整えられていきました。調子が出てきたタイミングで大樋焼の茶わんを手に各テーブルを廻る講師。完成形を掌に包んだことで、叩くアクション≒あふれる想いを結実させる道が見えたのか、何度も頷く子どもたちの姿がありました。
2点目は残りの土で自由造形。「自由」と聞いて喜んだのも束の間、参加者の視線が泳ぎ、天井を仰ぎ見る。そこで再び講師の声がけで「誰かを想う」手続きをとると、気持ちのブレが前のセッションよりも短時間で整って、目を開いた瞬間に自然と手が動き出します。そんなことある?と驚くくらいの変容でしたが、このたびの「ペチペチ」は叩く強さも間合いも人それぞれで、土を扱う現実を1点目である程度理解したのでしょう。器物は立ち上がりがスムーズで胴部の切れも一気に減少。使うシーンを想定したり、模様と質感との中間領域で心象を辿る子もいます。なかには器ではなくそこに盛る「ケーキ」「ピザ」などの食べ物や、人体や動物の造形も散見されました。

ワークショップの翌日、大樋長左衛門窯に運ばれた作品群は、着々と次のプロセスへと進んでいるに違いありません。子どもたちの生な想いは艶やかな釉薬に包まれて、これから「焼きもの」に結晶化し、別の相へと転ずるのです。自作と再会した参加者はどのようなリアクションを示すでしょうか。それについては作品の様子とともに、国立工芸館公式SNS等でご紹介したいと思います。
(『現代の眼』640号)
公開日:


