の検索結果
の検索結果
 No image
No image
ポケモン×工芸展来館者5万人達成記念セレモニーと『ポケふた』お披露目を行いました
2023年3月21日(火・祝)から開催しております「ポケモン×工芸展-美とわざの大発見-」が、このたび来館者5万人を達成いたしました。これを記念し、2023年5月16日(火)に来館者5万人達成記念セレモニーを開催いたしました。 来館者5万人達成記念セレモニーの様子 石川県金沢市からお越しの西谷様ご家族に、国立工芸館長 唐澤昌宏より「ポケモン×工芸展」のピカチュウぬいぐるみやロゴサコッシュなど記念品が贈られました。セレモニーには、着物姿のピカチュウも登壇しました。 併せて国立工芸館前に設置する『ポケふた』のお披露目を行いました。なお、セレモニーと『ポケふた』のお披露目は、同展に特別協力いただいている株式会社ポケモン様のご支援をいただきました。 国立工芸館前に設置する『ポケふた』とピカチュウ 「ポケモン×工芸展」は、お子様や20代30代の若い入館者が多く、大変ご好評いただいています。土曜日曜は大変混みあっていますので、来館される場合は、事前のオンライン予約をおすすめします。皆様のご来館をお待ちしております。 ポケモン×工芸展-美とわざの大発見-会期:2023年3月21日(火・祝)~2023年6月11日(日)開館時間:午前9時30分~午後5時30分 ※入館は閉館の30分前まで休館日:月曜日
 No image
No image
ある日のタッチ&トーク
活動紹介 〜 ある日のタッチ&トーク 担当:工芸館ガイドスタッフ Mさんテーマ:「総合芸術運動 身近なものを愛して」 1時: 工芸館に到着。今日のガイドのパートナーのFさんと一緒に〈タッチ&トーク〉の準備を始めます。受付横に案内板を出した後、〈さわってみようコーナー〉で作品のコンディションを1点ずつ確認し、お客さまがご覧になりやすいように並べていきます。 2時: ご挨拶をしてトーク開始。(慣れてきましてもいつも始まるときはとても緊張します。)10名ほどのお客様が参加してくださり、今回は2階の展示会場のご案内から始めました。 会場でのトークのテーマは「総合芸術運動 身近なものを愛して」です。アール・ヌーヴォーの中に日本美術のよさを再発見し、その総合芸術運動の影響から、幅広い活動を展開した浅井忠、橋口五葉、藤井達吉を中心にトークを進めていきました。 まずはミュシャのポスター《ジョブ》の前で、アール・ヌーヴォーの時代や美術様式について簡単にお話ししました。浅井忠のパリ留学時代のアパートの写真(ミュシャのこのポスターが飾られていました)や、アール・ヌーヴォーの名前の由来になったビングのお店の写真をご覧いただきながら、洋画家として知られる浅井忠のパリ留学時代の体験や、帰国後の工芸分野での活動につながるエピソードをご紹介いたしました。 橋口五葉の版画作品《髪梳ける女》では、ミュシャのポスターとの類似点をお客様にも考えていただきました。そして、橋口が浮世絵のよさを再発見し、アール・ヌーヴォーの装飾文様を着物や背景に取り入れながらモダンな美人版画の制作をしたことや、夏目漱石との交流からブックデザインを手がけるようになったことをお話しました。貴重な作品の数々に、お客様も興味を持ってくださったようです。 活動の様子(1) 次は浅井忠の工芸分野における活動の数々。漆芸家・杉林古香とのコラボレーションによる《鶏梅蒔絵文庫》の前では、作品の印象についてお話くださる方や、漆素材についての質問も出てきました。 最後は藤井達吉の《紺別珍地桐繍胴服》です。「芸術は、人間の実生活、家庭生活からかけ離れたものではない」とする藤井の芸術観と活動をご紹介し、刺繍、アップリケ、木彫、七宝など多彩な活動を展開した藤井の作品をご鑑賞いただきました。 2時35分: 1階の〈さわってみようコーナー〉へ移動。会場で漆の作品をご覧いただきましたので、今回は「漆とその技法について」というテーマで作品や資料をご紹介しました。 活動の様子(2) 山本英夫さんの《黒内朱汁椀》、《朱汁椀》と古伏脇司さんの《兎98-04》を比較しながら、漆のさまざまな表情 を見ました。また今回は、人間国宝の故・田口善国さんの蒔絵や螺鈿工程見本、鳥毛清さんの《うさぎのゆりかご》と沈金工程見本など、このコーナーのために 作家さんたちが提供してくださった作品や資料も揃えました。 作品に触れながら、つるつる、ざらざら、軽い!など、目で見ただけではわから ない重さや質感を実感し、発見があるたびにお客様の笑顔がこぼれました。お客様同士も次第に打ち解け、技法についての質問もたくさんでて、約1時間にわた る〈タッチ&トーク〉が和やかに終了いたしました。 いつも一期一会の出会いと、お客様と一緒に鑑賞できる時間を楽しみながら、〈タッチ&トーク〉を担当させていただいております。ご紹介するエピソードや、作品に触れてそのよさを一緒に味わいながら、作家の方々と工芸作品をより身近に感じていただけましたらうれしいです。
 No image
No image
タッチ&トーク
日ごろ身近な存在のうつわや着物。それが美術館のなかだと、ちょっと違って見えることはありませんか?素材の豊かな味わいや技術の粋を目にして、思わず「アァ!」と驚きの声をあげたり、「どうやって作るのだろう?」と首を傾げたことは? 「タッチ&トーク」は、そんな来館者の方々の声から生まれた鑑賞プログラムです。子どもから大人まで、どなたでも気軽に、深くじっくりと工芸の魅力に近づけます。ボランティアスタッフ(工芸館ガイドスタッフ)がご案内いたします。 〈タッチ&トーク〉ふたつの特色 さわってみようコーナー 人間国宝から人気の若手まで、さまざまな作家が精魂込めてつくりあげた作品の重さや感触など、目はもちろんのこと、指先のセンサーや音、時には匂いなど、五感をフルに使って味わいましょう。作家が実際に使っていた道具や、このプログラムのために用意された制作工程などの貴重な資料が登場することも。ガラス越しでは気づきにくい素材や技法の秘密に迫ります。 会場トーク ガイドスタッフと一緒に、参加者個々の「見る力」を探します。…といっても難しく考えることはありません。色やかたち、好き嫌い、そんな単純かつ短いフレーズから始めましょう。そこにはきっと、作品のエッセンスが隠れているはず!作家の素顔や制作にかける思い、時代背景など、さまざまなエピソードもご紹介します。
 No image
No image
お知らせ緊急バナー用
緊急情報について 工芸館のお知らせ緊急バナー用のリンク先ページです。 緊急情報がある場合はこちらに記事を投稿します。
 No image
No image
保存修復の取り組み
工芸館では、工芸やデザインのコレクションをよりよい状態で未来に残していくために、必要に応じて作品の修理、修復を行っています。特に工芸の場合、作品によって素材や技法が大きく異なるため、修復には分野ごとの専門家の協力が欠かせません。蛍光X線分析などを通して、作品についての新しい情報が得られることもあり、修復はコレクションの維持、研究において、大きな意味を持つ活動です。 事例1:鈴木長吉《十二の鷹》(2014年~2018年度修復事業) 変色・錆の修復、擦り傷等の現状保存修復および、架、架垂と大緒の復元 事例2:介川芳秀《彫金鹿衝立》(2017~2018年度修復事業) 錆付け 漆固め 事例3:加納夏雄《手板三種》(2017年度修復事業) 外枠組み立て クリーニング

鑑賞素材BOX(デジタル鑑賞教材)
作品の高精細画像を使って授業をしてみませんか?所蔵館を横断した取り合わせも可。作品の見どころや子どもたちの反応もご紹介しています。
 No image
No image
開館時間延長のお知らせ(4月29日~5月7日)
国立工芸館は、2023年4月29日(土)~5月7日(日)の9日間、開館時間を20時まで延長いたします。※入館は閉館30分前まで。
 No image
No image
館長挨拶
国立工芸館は、19世紀末期から現代に至る日本の工芸を中心に、広く国内外の工芸及びデザインを収集、保存、調査・研究、展示する東京国立近代美術館工芸館として1977年に開館しました。2020年には活動拠点を東京・北の丸公園から工芸が盛んな石川・金沢に移し、国立工芸館として新たなスタートを切りました。 いま日本の工芸はこれまで以上にアートへと領域を広げつつあり、多彩な作品群は世界からも熱い視線が寄せられています。当館は、新たな動向とその魅力をさまざまな活動を通して内外に発信し、世代や地域を超え、多様な人々と交流しながら工芸やデザインの素晴らしさをより強くアピールしていきます。 そして、これからも形式にこだわらない広い視点で、工芸及びデザインが発信するメッセージをみなさまにお届けします。 独立行政法人国立美術館国立工芸館館長 唐澤 昌宏
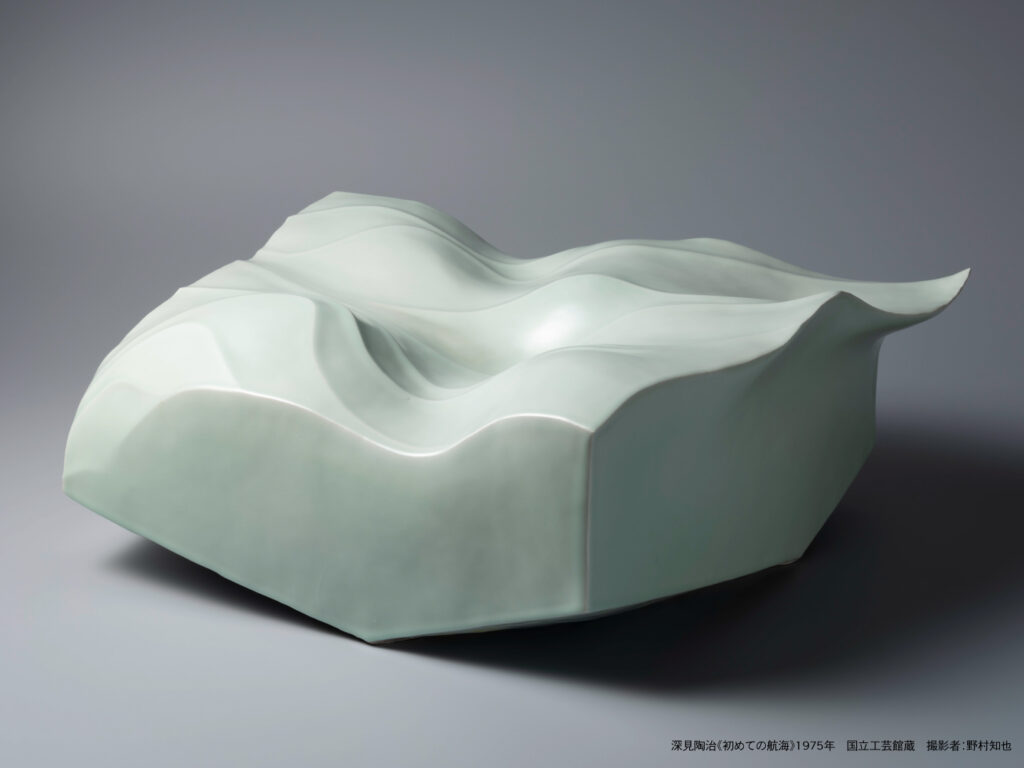
【「水の日」キャンペーン】
8月1日の「水の日」から4日間、受付で国立工芸館のSNSをフォローしていることがわかる画面を提示の方には国立工芸館オリジナルミネラルウォーターをプレゼント。その場でフォローもOK。 日時:8月1日(火)~8月4日(金)午前9時30分~午後5時30分 Twitter(@ncm2020) Instagram(@nationalcraftsmuseum) Facebook(@ncm2020.pr)
 No image
No image
ウェブサイトをリニューアルしました
2023年3月29日(水)東京国立近代美術館のウェブサイトをリニューアルしました。 東京国立近代美術館、国立工芸館それぞれのURLが変更となりました。お気に入りやブックマークなどに登録されている方は、お手数ですが新URLへの設定変更をお願いいたします。 旧ホームページURL)https://www.momat.go.jp/am/新ホームページURL)https://www.momat.go.jp/ 旧ホームページURL)https://www.momat.go.jp/cg/新ホームページURL)https://www.momat.go.jp/craft-museum


