の検索結果
の検索結果
花籃 静日
竹千筋組上飾箱
花籃 あんこう

【イベント】映写機で知る工芸の世界
国立映画アーカイブ所蔵の「工芸技術記録映画」を、映写機を使用して特別上映いたします。 予約受付は終了しましたが、各回お席に余裕がありますので、定員まで当日参加可能です。 場所:国立工芸館2階多目的室定員:各回40名(要予約・先着順)参加費:無料(ただし、上映日当日の展覧会観覧券が必要です)作品:①8月11日(金祝)17:50~(受付17:40~)『工芸技術記録映画シリーズ30 萩焼―十一代三輪休雪の鬼萩―』②8月11日(金祝)18:52~(受付18:42~)『工芸技術記録映画シリーズ13 型染め―江戸小紋と長板中形―』③8月12日(土)17:50~(受付17:40~)『工芸技術記録映画シリーズ11 髹漆―増村益城のわざ―』④8月12日(土)18:47~(受付18:37~)『工芸技術記録映画シリーズ21 鋳金―齋藤明のわざ―』
 No image
No image
アートライブラリのご案内
国立工芸館アートライブラリは、主に近・現代の工芸・デザインに関する資料を所蔵する専門図書館です。国内外の工芸・デザインに関する作品集、展覧会カタログ、各種美術参考図書などを約3.5万冊、美術雑誌を約1,500タイトル所蔵しております。所蔵資料の閲覧を希望される方は、どなたでも無料でご利用いただけます。 ご利用の際は以下の点に、ご協力お願いいたします。 資料閲覧、蔵書検索(OPAC)用パソコン使用前後の手指消毒 ご利用案内 開室日 展覧会開催中の火曜日~金曜日(週4日)休室日:土・日・月曜日、祝祭日、休館日、展示替期間、年末年始および特別整理期間 開室時間 13:00-17:00入室受付は16:30まで お願い コートや鞄などは、閲覧室には持ち込めません。 貴重品、筆記用具以外はロッカーにお預け下さい。 傘は傘立をご利用ください。 閲覧室内では携帯電話、スマートフォンの使用、飲食、喫煙はご遠慮下さい。 図書閲覧方法 当室の資料の大部分は閉架書庫にあります。閉架図書利用にあたっては閲覧申請書にお名前、ご住所を記入の上、検索用端末でご希望の資料を検索し、書名と請求番号を記入し、カウンターへお持ちください。(5冊まで) 所在=第II閉架は、請求当日の出納閲覧はできませんので、お問い合わせください。 資料の状況により、閲覧ができない場合がございます。資料の状況は蔵書検索にてご確認ください。 当室の資料は、館外への貸出しはおこなっていません。 複写サービスをご利用いただけます。 複写サービス 当館ライブラリの所蔵する資料については、著作権の範囲内で行っております。ただし、資料の保存上、問題のないものに限ります。 受付時間 13:00-16:30 複写料金 モノクロ30円、カラー100円 申し込み方法 複写申請書に複写希望箇所・お名前・ご連絡先を記入の上、複写希望資料の該当箇所にしおりを挟んだ状態でカウンターまでお持ちください。スタッフが確認の上で複写料金をお伝えするので、お支払いをお願いいたします。スタッフがご希望箇所を複写いたします。 ご注意 1回に申請できる資料の点数は5点までです。 1回の複写枚数は50枚までです。 複写範囲は著作権法により制限されています。著作権の保護期間にあるものに関しては、著作物の半分を超えて複写することはできません。 利用目的は個人的な調査研究に限ります。 特定の資料に関しては、保存上などの理由により複写できない場合もあります。 一旦支払われた料金については、払戻しができませんのでご注意ください。 複写は、当室の資料に限ります。 スマートフォンやカメラでの撮影はご遠慮下さい。 事前申し込み 所在=第II閉架の資料をご利用される場合は、事前申し込みをお願いいたします。 ご利用希望日の3日前までにお申し込みください。 閲覧できる資料は5冊までです。 工芸館の資料(所在=工芸館*)に限ります。 閲覧資料の当日の追加・変更はできません。 資料の状態により、閲覧・複写をお断りすることがございます。ご了承ください。 複写の受付は、閲覧時間終了30分前までとなります。 申し込み方法 下記必要事項を記入の上、cglib-yoyaku@momat.go.jpまでご連絡ください。折り返し担当よりご連絡いたします。 利用者氏名:複数名の申し込みは出来ません。 連絡先(TEL):連絡の取れる電話番号をご記入ください。 希望日時:開室日カレンダーをご確認のうえ、来室希望日時をご記入ください。 資料タイトル、資料ID:5冊まで。蔵書検索で調べてご記入ください。 ご記入いただいた個人情報(氏名、電話番号等)は、本閲覧業務に関すること以外では利用いたしません。ただし、以下の場合においては、個人情報を開示することがあります。 法令の根拠に基づき、開示を求められた場合 公的機関(保健所等)からの正当な理由に基づく要請のある場合

【\こども/工芸トークオンライン】2023年8月
※満席となりました 工芸トークオンラインは高精細画像を見ながら対話を通して鑑賞を深めるプログラムです。こどもには工芸はむずかしそう?いえいえ、大丈夫!高精細画像ならではの迫力を堪能しながら、のんびり楽しくおしゃべりしましょう。「水のいろ、水のかたち展」の出品作の中から1点を参加者の皆さんとじっくり味わいます。 プログラム概要 8月20日(日)11:00(約30~40分) 無料 6名程度 5歳~小学生以下の子どもを含むご家族 zoomミーティング
 No image
No image
刊行物
東京国立近代美術館では、種々の出版物を刊行しています。 カタログ・図書・目録 これまでに刊行した展覧会のカタログや図録、目録をご紹介します。蔵書検索システム(OPAC)より一覧をご確認いただけます。また一部の書籍はショップにて郵送販売も行っています。 現代の眼 東京国立近代美術館、国立工芸館で開催される展覧会の特集記事や所蔵作品の解説、作家によるエッセイや、美術館の教育普及活動などを載せた美術館ニュース『現代の眼』は、1954年の創刊以来636号まで刊行してまいりました。当初はモノクロ8ページの月刊でスタートしましたが、1996年4月より部分カラー16ページの隔月刊へと移行。2013年の600号の節目を機に、オールカラー化しレイアウトを一新しました。その後2017年4月より季刊化。そして2020年より、より多くの方にご覧いただけるよう電子ジャーナルとして生まれ変わりました。 研究紀要 東京国立近代美術館・国立工芸館は1987年より『研究紀要』を発行しています。当館アートライブラリのほか、全国の主要大学、研究機関でご覧いただくことができます。また、第11号以降は東京国立近代美術館リポジトリでも公開されています。 活動報告 これまでの東京国立近代美術館の活動をまとめた報告書です。東京国立近代美術館リポジトリより、全文PDFをご覧いただけます。

多様化する工芸の現在地
“工芸とは何か” そのような問いに対し、工芸の現在地が俯瞰できる「ジャンルレス工芸展」が国立工芸館で開催された。本展では、国立工芸館が所蔵する工芸・デザイン作品を中心に、敢えて工芸と括らずに新たな視点で紹介することを目的としている。まず会場を訪れると「デザイン」と「現代アート」という従来の工芸からは少し離れた印象を持つエリアに区分されていることに驚かされる。しかし同時に、共感に近い感覚も覚える。最近では、私自身も含め、美術や工芸といったジャンルに拘らずに工芸素材や技術に向き合う作家が増えてきているからだ。 まず、「デザイン」部門である展示室1に入ると、富本憲吉の《色絵金銀彩羊歯文八角飾箱》に出会う。単純形態を連続させることで、新しい図柄を生み出すという富本独自の意匠は、未だに新鮮で洗練された印象を抱かせる。2階に上がった“芽の部屋”では令和に活躍する作家である見附正康、新里明士、池田晃将、澤谷由子らの緻密な意匠が鑑賞できる。池田晃将の《電光無量無辺大棗》[図1]では、現代の情報化社会を背景に映画「マトリックス」を彷彿させる意匠が印象的だが、その基盤には精密な螺鈿技巧が存在する。また、澤谷由子の《露絲紡》では、レース編みを彷彿させる西洋的な雰囲気を纏った意匠が見られるが、そこにはイッチン技法[1]を追求した先にのみ表現できる唯一無二の世界観が広がっている。漆の神様と呼ばれる松田権六が「技術と材料を生かす根本はデザインなんです」[2]と語っているように、やはりデザインが面白くなければ魅力ある作品は生まれないのだと実感する。これらの作品を見ると、従来の工芸では思いも寄らなかった表現対象とも言える独自の世界観が、技巧を尽くした確かな工芸手法の上で表現されていることに気付かされる。こうした意外性が現代に通用する魅惑的な美を備えた作品へと昇華させていくのだろう。 次の「現代アート」部門では現代陶芸のパイオニアとも言える八木一夫の《黒陶 環》や社会性を取り入れた幅広い表現を行う三島喜美代の《Work-86-B》など、まさに現代アートと言われる作品の数々が並ぶ。坪井明日香の《パラジウムの木の実》[図2]では、女性の乳房が積み上げられた中心に1房のぶどうが添えられており、女性が排他的に扱われていた制作当時、アバンギャルドな作品であったことは想像に容易い。メタリックな質感でありながらも陶芸作品であるという点にも見所がある。また、牟田陽日の《ケモノ色絵壺》では、九谷焼独特の色彩を活かし、華やかな花々に囲まれた中に構える白い山犬が臨場感たっぷりに描かれており、その求心力に惹き込まれる。いずれの作品も各々の表現したい世界が明確にあり、工芸の素材や技術を1つのツールとして捉えながら、自らの表現を探求しているように窺えた。 本展を通して、“工芸とは何か”という、おそらく工芸に携わる多くの現代作家が一度は考えるであろう問いに対し、工芸を基盤にしながらも現代アートやデザインに果敢に拡がっていく工芸の現在の有様を俯瞰することで、改めて工芸の現在を考えさせられた。元来、歴史や伝統を重んじる工芸には「古臭く技巧的で職人的」[3]と思われる側面があったかもしれない。しかし、私を含めた現代作家は、先達が切り拓いてきた道があるからこそ自由に表現でき、そしてそれが評価される時代に今、生きているのだと実感する。今後、益々拡がるであろう工芸の可能性に期待が膨む。 (『現代の眼』637号) 註 筒状の泥漿を作品に盛り付ける装飾技法であり、陶磁技法の一種。 NHKアーカイブス「あの人に会いたい 松田権六」より引用。 岩井美恵子「時代の芸術—ジャンルレスな時代の工芸とデザイン—」、『ジャンルレス工芸展』(図録)、国立工芸館、2022年、p.4
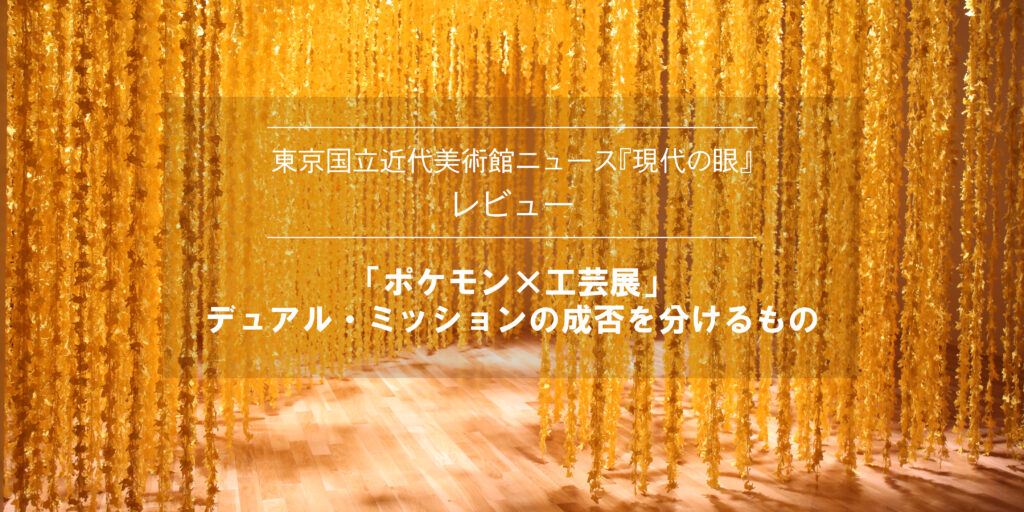
「ポケモン×工芸展」:デュアル・ミッションの成否を分けるもの
「ポケモン×工芸展」。とてもわかりやすい展覧会名だ。ポケットモンスターを「お題」にした工芸作品が見られるのだろう、ということがよく伝わってくる。しかも出品作品のすべてが新作だという。キャリアのある作家から新進作家まで、20名の作り手たちの技と創意を、ポケモンという統一された図像体系(イマジュリー)を通じて鑑賞できるわけだ。ポケモンのことは何となく知っている、という程度だったが、未知の図像体系に支えられた異文化の文物を鑑賞するような心持ちで展示を楽しむことができた。 金沢での現代工芸の展覧会といえば、「工芸未来派」(2012年、金沢21世紀美術館)のことが思い浮かぶ。「工芸未来派」では、今展のポケモンに相当するような統一テーマがなかった。キュレーターが後に出版した同名の書籍を見ていると、「現代工芸って何でもアリなんだな」という印象をさらに強くする。それは課される枠がないことからくる野放図さ、自在さの印象といえるだろう。他方、「ポケモン×工芸展」では、お題があることで一種の枠が課されている。作り手は野放図に新作を送り出すわけにはいかない。ポケモンの図像体系に「準ずる」ことは、今回、工芸作家にとってはひとつの大事なミッションなのである。 話は変わるが、学芸員時代に「ウルトラマン・アート!」という巡回展の担当をした。怪獣のデザイン画を始めとする放映当時の資料のほか、ウルトラマンにインスパイアされた現代美術(映像を併用したインスタレーション)も出品されたのだが、そのインスタレーションでは、演出された「チープさ」を通して、皆が知っているフィクションに対する愛情と批評的態度が表現されていた。「ポケモン×工芸展」の会場では、こうした「チープさ」が感じられない。大抵の作家と作品が、いたって大真面目に見えるのだ。そうした印象は、友禅であれ、螺鈿であれ、自在であれ、会場のほとんどすべての作品がラグジュアリーに見える(すなわち「チープ」ではない)、ということと無関係ではないだろう。この真面目さの印象は、一体どこから来るのか。私にはそれが、素材や技法に「殉ずる」工芸作家たちの制作態度に由来しているように思われた。 「ウルトラマン・アート!」におけるインスタレーションは、コンセプト重視である。そこで用いられていた素材や技術は、演出上必要ではあっても、比較的容易に代替可能な要素の集まりである。他方、多くの工芸作家にとって、素材や技法は簡単に他で代用できるものではない。それらは、工芸作家のアイデンティティの一部をなしていたり、作り手たちがもつ世界観と切り離せないものだったりする。だから、お題にあわせて素材を替えてしまう、というわけにはいかないのだ。「ポケモン×工芸展」において、お題が外部から要請されたミッションであるとするならば、自らが選び取った素材や技法にこだわることは、工芸作家が自身に課している「もうひとつのミッション」であるといえる。これらのミッションが首尾よく果たされるかどうかは、作り手の側からすれば、素材や技法の特性を活かして、お題を納得のいくかたちで造形化できるか、に懸かっている。国立工芸館の側からすれば、ゲームやアニメというフラットな世界への来場者の関心を、三次元の厚みと素材感のある表現、そして作り手が日々身を投じている物質的現実との真剣勝負、いわば工芸の世界への関心へとさりげなく拡張することができるかどうか、ということになるだろう。 オープンして最初の週末、修学旅行なのか、会場は制服姿の中学生たちで溢れかえっていた。螺鈿の作品を見ていると、「これって貝殻なんだ」「(貝殻は)角度が変わると色が変わって見えるじゃん」「すごい…」という学生の会話が聞こえてきた。POKÉMONもKOGEIも、国際的な認知度が高い日本発のコンテンツだ。会場で出会うラグジュアリーな作品の数々は、そうした認知と期待に十分応えるものになっていると思う。でも、そうした期待に応えられていること以上に重要なのは、こうした子どもたちの反応のほうだろう。次代を担う若者たちの口からもれてくる、「これって貝殻なんだ」という素材や技法に対する素直な驚きの声。工芸の未来はおそらく、そこに懸かっている。ポケモンを入り口にしつつ、そうした感想が会場でどれだけ呟かれるのか。それこそが今回、工芸作家と国立工芸館が臨んだ二重(デュアル)の(・)使命(ミッション)の成否を分ける本当の基準なのだと思う。 (『現代の眼』638号) 池田晃将《電線光環中次》2022年 個人蔵©2023 Pokémon.©1995–2023 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.撮影:斎城卓 吉田泰一郎《ブースター》2022年 個人蔵©2023 Pokémon.©1995–2023 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.撮影:斎城卓

先生のための工芸館タイム
小・中・高等・特別支援学校の先生方を「水のいろ、水のかたち展」にご招待します。工芸を題材とする鑑賞授業のイメージづくりに、学外研修にご活用ください。図画工作・美術専科以外の先生も大歓迎です。 実施期間 7月21日(金)~9月24日(日) 当日の入館について 小・中・高等・特別支援学校の教員であることが確認できる身分証(職員証、保険証、名札など)を受付にご提示ください。受付にて、学校名、氏名の記入をお願いいたします。ご提供いただいた個人情報は、本プログラムの実施状況確認以外には使用いたしません。ご協力をお願いいたします。


