見る・聞く・読む
現代の眼 オンライン版 展覧会レビュー 工芸の光と影—漆黒の闇—
戻る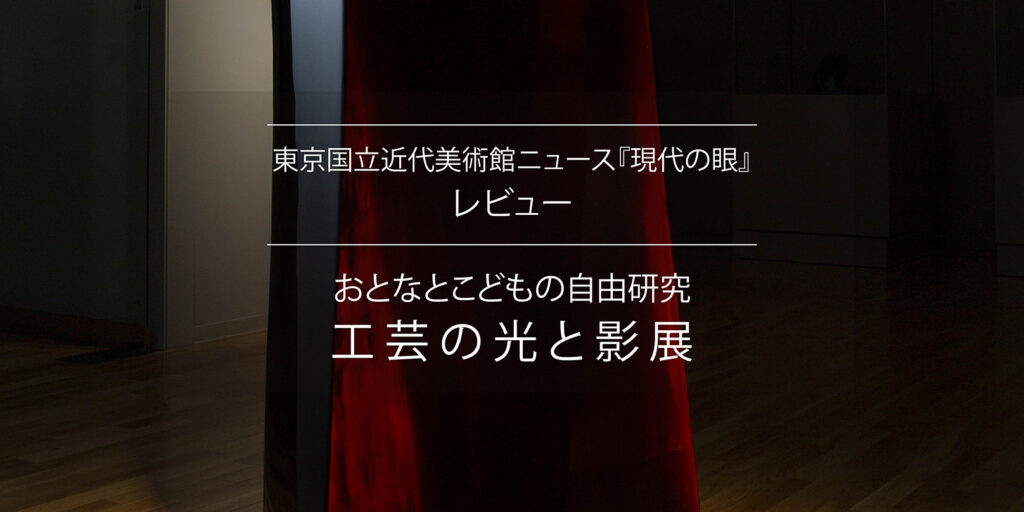
「光と影」をテーマとした展覧会は工芸では少ないのではないか…担当研究員から展覧会の趣旨をお聞きして、まず私はそう思いました。一般的に美術または現代美術と言われている表現領域では、光や影をテーマにした展覧会や作品は多く見られますが、工芸では作品展示で照明等に気を使うことはあっても、光と影という視点からの展覧会は珍しいと言えるでしょう。
私は漆を用いて作品を制作していますが、作家として歩みはじめた30代はじめの頃から光を表現の一部として意識してきたように思います。光を照明効果や現象としてではなく、表現の要素の一つとして捉えてきました。谷崎潤一郎の『陰翳礼讃』をもちだすまでもなく、漆は光によって異なる表情を見せます。そして光によって引き出される漆の艶や質感から私は表現を考え制作を行ってきました。例えば漆黒と呼ばれる漆ならではの透明感のある黒い塗面には、ただの色彩の黒ではない影と闇が同居しているように私には思えます。ジョン・ハーヴェイの著作『黒の文化史』に、「原初は概ね暗闇からはじまる」という一節がありますが、私はこの言葉のように漆黒を原初と重ね合わせながら創造性をかきたてられて制作することもあります。一方、朱漆は光によっては官能的にまるで生きているかのように感じます。光、そして影は、作品の造形上の凹凸による陰影の変化を表すだけではなく、人間の精神に作用する働きをも持つと言えるでしょう。

今回展示されている《Inner Side-Outer Side 2011》は、通常器物などに保護や美観として塗られている漆を、漆皮膜だけで自立した立体として表現しました。原型制作から乾漆の工程を経て塗りや磨きの作業に至るまで、私は一貫して手の感触、触覚的な要素を大事にしながら制作を行っています。自立する漆膜の断片として存在する形の根底には、器に対する私の思考があります。器を単に何かを入れる道具の形としてではなく、身体の一部或いは象徴として捉え、内と外の意味を考えて制作したものです。《Inner Side-Outer Side 2011》は、人間を包み込むような身体を超える大きさとなっており、立ち上がった漆黒の外面は磨きあげられた鏡面仕上げにし、鑑賞者を闇に吸い込むように妖しげに空間に存在します。内面には人間の体内、或いは内に秘めた情念を思わせる朱が荒々しく塗り込められています。外面と内面のそれぞれの世界が、光と影によって強調的に引き出されています。
最後にもう一つ別の黒い漆作品を取り上げたいと思います。それは展示室2に展示されている三代渡辺喜三郎の《丸棗》です。1909年、江戸時代から続く塗師屋に生まれ、昭和になって活躍した漆芸家による作品です。木地から塗りまで薄手に仕上げる洗練された作風で知られています。加飾もなく塗りだけのあまり目立たない作品ですが、手のひらで包み込むと気持ちがいいであろう小さな球体の形をした棗です。最初に展覧会を見た時には印象に残らなかったのですが、展覧会場を何度か見て回るうちに、徐々に漆黒に妖しく輝くこの作品に私は引き込まれていきました。工芸館を出た後も、脳裏からしばし消えることはありませんでした。小さいながら漆黒の塗膜で覆われたあの作品はなんなんだと…。

いい形とか装飾が美しいとかではなくて、“これが漆だ”と思えるような作品を作りたいと常に思っている私に、あの丸棗は問いかけてくるようでした。
漆、この不思議な樹液から創作への欲求を駆り立てられ、今を生きる私の表現として、痕跡として、これからも私の制作は続きます。
(『現代の眼』639号)
公開日:


