見る・聞く・読む
現代の眼 オンライン版 展覧会レビュー デザインと工芸と快適な暮らし
戻る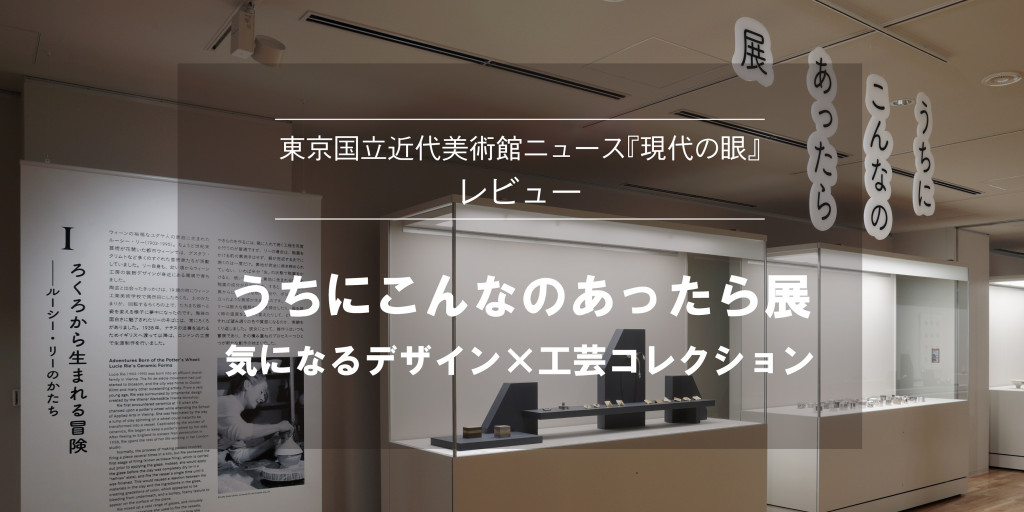
「工芸館」と呼ばれていた東京・竹橋の「東京国立近代美術館工芸館」が公式通称として「国立工芸館」(以下「工芸館」)を名乗り金沢に移転したのは昨年10月末のこと。早いものですでに4か月が過ぎ、石川移転開館記念展も現在第2弾が開催中である。それが「うちにこんなのあったら展 気になるデザイン×工芸コレクション」であり、デザインと工芸の両分野を所蔵する工芸館の強みを生かした展示となっている。
現代の日本における「工芸」とは、古来の中国で意味していたような単なるもの作りを示す「工業」と同義ではなく、「表現としての工芸」を指す[註1]。この「表現としての工芸」は用途を持ったものから持たないものまで多種多様で、例えば一人の工芸家がどちらも制作することはよくあることだし、さらには、大量生産のためのデザインのみ行うこともある。また工芸家でもデザイナーでも使用を意識して制作する場合、自身の作品が人々の生活をより快適で美しく彩りあるものにすることを願う。「うちにこんなのあったら展」は作り手のそのような意識が見えるとともに鑑賞者が自宅に欲しいと思えるような、選ばれし約200点の所蔵作品が展示されていて、まさに理想の暮らしを夢見る空間となっている。
本展は3名の作家を軸に構成されているが、最初に登場するのはルーシー・リー。「飾ること」や「かたち」をキーワードに、彼女を人気作家に押し上げた華奢な形態の器や、知る人ぞ知る可愛らしいボタンやネックレスなど、工芸館が所蔵する全13点を展示、彼女の幅広い作風がよくわかるようになっている。本章後半ではテーマを「ティータイム」とし、バーナード・リーチやユッタ・ジカ、石黒宗麿、濱田庄司といった作家によるティーセットがずらりと展示されていて壮観である。
続いては富本憲吉である。富本は「模様から模様を作るべからず」という信念で図案を制作、その独自の模様を生かした色絵磁器で重要無形文化財保持者いわゆる人間国宝に認定された一方で、量産陶器の製造を模索するなどデザイナーとしての一面も評価されている作家である。本展では前者を代表するものとして「四弁花」の飾筥(かざりばこ)が、後者の一例として涼やかな花字紅茶碗のセットが出品されている。さらに機能性抜群ながら象の鼻のような可愛らしい注ぎ口の森正洋《G型しょうゆさし》や、文字を文様化した田中一光のポスターで、日常に溶け込みながらも印象的に人の心に留まるデザインを知ることになる。
最終章はクリストファー・ドレッサーのデザインが中心だ。ドレッサーやエミール・ガレの手になる異国趣味の作品から、ピエール・シャローによるアール・デコのフロアー・スタンドなど、ヨーロッパのデザイン運動を把握できるようになっているうえに、用と美を問う杉田禾堂(かどう)の作品や杉浦非水の「東洋唯一の地下鉄道」開通ポスターによって昭和初期の日本のモダンデザインの流れを追うことができる構成だ。これらすべて、今見ても新鮮に映るデザインたちである。
これまでの行動や生活様式の変容が求められ、家にこもる時間が増えたこの一年。多くの人が、身の回りに関心を向けるようになったのではないだろうか。より「美しく」「心地よい」モノに囲まれたい。自分の半径2mを見つめなおすとき、本展に出品されたデザイン作品や工芸作品を思い出すことで、日々の暮らしの充実を図ることができるに違いない。するときっと毎日が楽しくなる。
(『現代の眼』635号)
註
1 木田拓也「日本における工芸の誕生」、『別冊太陽 工芸の国、ニッポン』(平凡社、2020年12月)、15頁。
公開日:


