の検索結果
の検索結果
 No image
No image
長浜重太郎
 No image
No image
武腰潤
 No image
No image
清水保孝
 No image
No image
伊勢崎紳

工と芸との間に―国立工芸館の立つ丘で
美術は外来概念であったが、工芸は漢語であった。工芸は古来から「たくみのわざ」全般を意味する言葉であり、現在のような美術の下位概念の1つを指してはいなかった。明治日本は美術の移植に伴って、工芸をその一部に位置づけた。つまり、近代日本において工芸は美術の双子として育ったが、これによって日本美術は西洋から大きく逸脱せざるを得なかった。しかも、後進工業国日本にとって、手仕事は重要な輸出品製作の手段でもあったので、美術はその領域と自らを峻別しようとした。これらの経緯が近現代の表現領域で、工芸を卑屈にさせることになった。それは結果として技法的完成度を至高とする評価の袋小路に自ら閉じ籠もって自足する結果を招いた。 国立工芸館が金沢に移転するに際して、その開館展のサブタイトルに「素材・わざ・風土」を掲げたことはまことに至当だと、我が意を得た。なぜなら、ポストコロニアルがヨーロッパを範とする近代の呪縛からの解放を美術にも及ぼした今日、工芸にあたわった可能性は前近代に根差す表現の手法、素材、様相に潜んでいるからなのだ、と言っておきたい。本展においても加守田章二から室瀬和美まで造形意欲よりは技法と素材をあらわにする作品が選ばれ、1970年代から次第次第に工芸分野で美術の脱構築が進行していることに改めて気づかされた。 仕事場の再現ばかりか、展示スペースのかしこに登場する松田権六こそは近代日本の工芸の歩みを体現した作家だと思う。金沢に生まれ、東京美術学校卒業制作において近世の伝承を飛び超して自由闊達に自己を表現するところから出発しながら、パイロット万年筆、日本郵船)と実社会に生きる蒔絵制作に踏み込み、近代における工芸の不利を優位に転換させたわざはいまなお感嘆に値する。通常なら《蒔絵螺鈿有職文筥》の世界に留めておく評価軸を《片身替塗分漆椀》の感覚にまでに及ぼしている本展の視野は特筆に値する。つまり、松田の評価を伝統の意匠と技法の完成度に留めおかないで、漆器が日常に息づいて心弾ませる意匠と手になじむ器形のゆえに、人々に親しまれる魅力までに広げて見せているのだ。このことは国立工芸館が提示しようとする工芸の世界を工芸作品の制作と受容の現実に即した位相から見せようとするだけでなく、美術を超えて開かれていく可能性を指し示そうとする営みを示してもいよう。 工芸の語は人間の手わざを指す工と、芸術的価値を指す芸から成り立っている。例えて言えば、本展でも取り上げられた茶の湯のごとく、芸の真実を日常のなかで育んできた日本の有り様を踏まえるならば、工芸という領域に手わざと美とを統合して愛好する理由が分かり易くなる。純然たる技術としての工芸とそれによって作られた作品が醸しだす世界を身の内から糾いだそうとするのが工芸作家であり、工と芸との間を一身でつなごうと存在するかのようだ。それは一方で技術的な修練・完成と他方で地域環境に由来する芸術性とをひと時に味わおうとする営みだ。この流儀はポストコロニアル下で、我々が地域の創造に見つけている価値観に通底しているがゆえに、伝統工芸が生き延びた街の一角に国立工芸館がいま降り立つにふさわしい時機なのだと感じないではいられない。 (『現代の眼』635号)
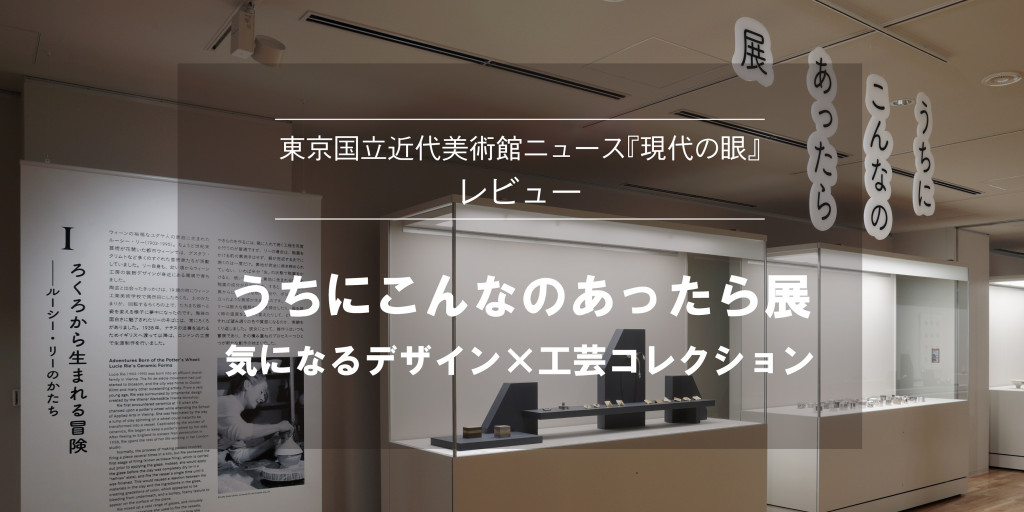
「うちにこんなのあったら展」を観たら。
金沢に移転した国立工芸館では、石川移転開館記念展IIとして「うちにこんなのあったら展」を開催している。本展では、クリストファー・ドレッサー、富本憲吉、ルーシー・リーを軸に、工芸館のコレクションから厳選したデザイン・工芸品を紹介している。タイトルの「うちにこんなのあったら」は、使ってみたいと想う気持ちを表しているとともに、作り手にとっては、人々に向けて作るときの原動力ともなっている。本展には、快適で美しく、彩りのある生活を夢見たデザイナーや工芸家達の作品があふれていた。 本展を見て、感じたこと、気づいたことなどを少し書いてみたい。私はテキスタイルデザイナーなので、染織のことはわかるが、例えば陶磁器、彫金・鍛金、家具などにはまるで門外漢である。今回の展示品は、富本憲吉、ルーシー・リーを軸としていることもあり、陶磁器の作品が圧倒的に多かった。「うちにこんなのあったら」と想う側の人としては、それらの陶磁器は、どれもうちにあったらと想うばかりであった。そうした中で、3点ほど気になった作品があったので記す。 1つは富本憲吉の紋様についてである。野山を歩いてデッサンし、独自の模様を作り、それらを多様に展開してきた富本の陶芸作品は、これまでも美術館、博物館などで鑑賞し、そのたびに感動してきた。今回は、初期の作品である素朴な絵付けの鉢、皿、そして野の草花の模様が可憐な色絵染付、そして白磁など、美しいフォルムの作品が展示されている。富本の作品の中に着物、帯の作品があることは知っていたが、今回の展示では帯の展示があった。それは古代紫色の「金彩草模様帯(きんさいくさもようおび)」。私はその模様に釘付けになった。金彩で描かれた模様は秋草だろうか、生き生きと描かれた草の動き、そして抽象化した菱紋は布地全体を埋め尽くしており、リズミカルに広がっている。丸くくり抜いた形状からは、自分自身の大皿、陶板の作品を写生し、染織デザインのモチーフとしたのではないかと想像を巡らす。確かに富本の独創的な陶芸作品は、それ自体がデザインの要素にもなり得る。目的に合わせ、それぞれの仕様に合わせ、素材の異なる工芸品に転用できる。工芸、デザイン、工業の間の垣根を軽々と超えている富本の凄さを感じた。また2つ目は、展示品の中の小さな「醤油注」3点、可愛らしく並んでいる。同じ形の醤油注に、異なる絵付けの施された手工芸品に見えるが、よく見比べてみると、1つはシャープで傾斜があり注ぎ口は少し上向き、残る2つは膨らみのあるフォルムで注ぎ口もふっくらしている。最初のものは手仕事の工芸品、2つ目は量産品のための見本、最後の一品は量産品とのこと。ここでも手工芸とデザイン(量産)をつなぐ、あるいは超える富本の先見性を見いだした気がした。富本の量産の醤油注、そして森正洋の「G型しょうゆさし」は、「うちに こんなの ある」可能性は高い。 さて3つ目は、森正洋の作品。森の最後の仕事は無印良品のためのシンプルで美しい白い「和の器」シリーズと言われている。その中の「汁差し」は、丸く可愛らしく親しみやすい形だったことを思い出した。このシリーズは、森が50年以上もデザインを手がける長崎の波佐見で仕上げた磁器のシリーズ。森正洋は、小さな日常の道具を通し、手仕事の工芸と大量生産のデザインとを、富本とは違った方法で結びつけたのではないだろうか。森は富本とは異なり、大量生産を前提とする現代の社会を意識し、デザインに手工芸のエキスを持ち込もうとしたのではないだろうか。森は工芸家と言うより、工芸を深く理解する優れたデザイナーであった。 工芸家でありながら、デザイン(量産)と工芸の垣根を軽々と超える富本憲吉。数十年間にわたり、大量生産を前提として優れたデザインを残した森正洋の手工芸とも呼べる作品群。両者は「“工芸は、片方の手で美術と、またもう一方の手で工業とつながる領域と言われます。”」を体現した2人だと確信した。 (『現代の眼』635号)
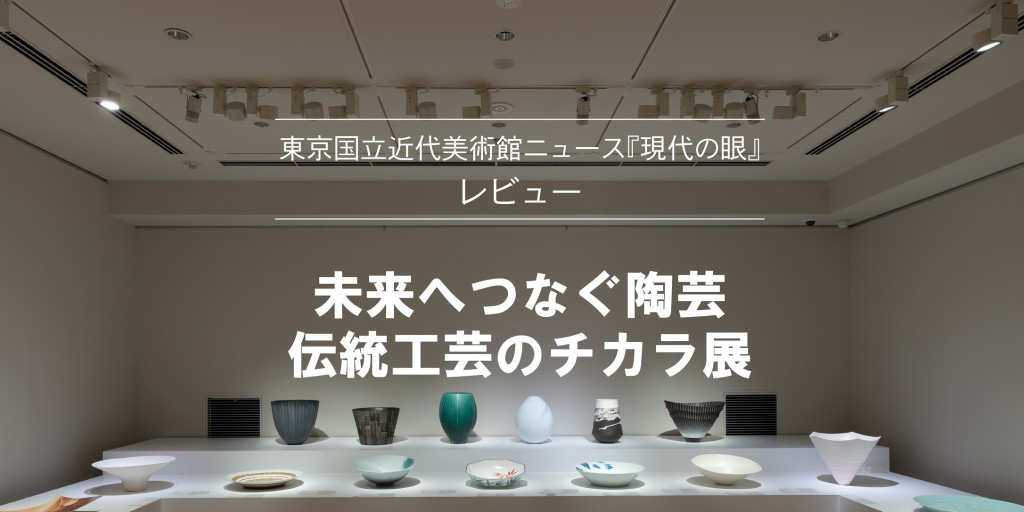
伝統工芸のある未来
東京国立近代美術館工芸館が、日本きっての工芸都市である石川県金沢市に移転すると聞いた時はとても驚いた。しかし、工芸というものが本来、持っている特性や成り立ちを考えると、なかなか面白い展開でもある。工芸とは、その土地の風土に根ざしたものであり、そこで育まれた自然の素材と技術から生み出され、人々の生活に寄り添いながら、それぞれの時代の求めに応じて発展してきた。そして、その多くは地方にある。移転のきっかけは、国の地域創生施策の一環であったかもしれないが、通称「国立工芸館」とその名を改め、ここから日本の現代工芸を俯瞰しつつ、新しい時代の新しい工芸を新しい価値観で捉えていく、そんな未来の姿(希望)がちらりと覗く。移転後、初めての陶芸展となる「未来へつなぐ陶芸—伝統工芸のチカラ展」は、まさに時機を得た、そして、待望の展覧会であったのではないだろうか。 本展は、日本工芸会において最大会員数を誇る陶芸部会が2022年に活動50周年を迎えることを記念して企画されたもので、私が勤務する兵庫陶芸美術館を含む全国8か所の美術館を巡回する。日本工芸会は、1950年に制定された文化財保護法が、1954年に一部改正され、翌1955年に重要無形文化財保持者(人間国宝)の認定制度が始まったことを機に発足した。選定基準が「衰亡の虞のあるもの」から「(一)芸術上特に価値の高いもの (二)工芸史上特に重要な地位を占めるもの (三)芸術上価値が高く、又は工芸史上重要な地位を占め、かつ、地方的特色が顕著なもの」[1]へと改変されたことで、技術だけでなく、優れた芸術性と新しい表現が求められるようになったことが、何より大きな転機となった。「伝統工芸」という言葉は、言葉の持つイメージに反してじつは比較的新しく、戦後、日本伝統工芸展を中心に活動する日本工芸会の会員たちの精力的な活動を通して定着してきたものである。伝統というと、どうしても古臭いイメージが拭えないが、根幹にあるのは「革新」、つまり、時代ごとに新しいものを加え、いかに「未来へ繋ぐか」という大きな使命を擁する。本展はまさにそのことを明らかにしようとするものである。 本展の構成は3章立てで、各章にコラムが2つずつ入る。伝統工芸の「確立」、「展開」、「未来」を緩やかに追いながら、日本工芸会と勢力を二分してきた日展の「創作陶芸」、1955年に陶芸分野で初めて認定された「重要無形文化財保持者」、「産地と表現」、「茶の湯のうつわ」、「素材と表現」、「新たな技法とうつわのかたち」というテーマに沿って選ばれた作品をコラムに挟み、伝統工芸の成り立ちや転換期、未来を予感させるような革新的な造形をより浮き彫りにしようとしている。137名の作家による139点の作品が一堂に会するとじつに圧巻で、何よりその美しさ、力強さ、多様さには驚くばかりである。しかし、一方で、これまで順守されてきた伝統工芸のいわば「不文律」による、一様の清廉せいれんさが気になりもする。一つ一つの作品を見るとどれも生き生きとして素晴らしいが、ずらっと一列に並んだ時に感じる「規格が揃っている」という印象。じつは、そこに揺さぶりをかけようとするのが本展の一つの意義ではないだろうか。それは、改めて「伝統工芸とは何か」を再考することでもある。 しかしながら、エポックメイキングな作品というのは、一際、存在感を放つものである。「練上手ねりあげで」の技を極め、タブーとされる亀裂を造形に活かした松井康成の《練上嘯裂しょうれつ文大壺》(1979年)、伝統的な九谷焼の上絵の具を抽象表現へと高めた三代德田八十吉の《耀彩ようさい鉢 創生》(1991年)、産地ならではの問題を逆転の発想で打ち破り、新しい素材を創出した隠﨑隆一の《備前広口花器》(2012年)、彫刻的フォルムの洗練された美しさで圧倒し、伝統工芸のフォルムの常識を変えた和田的あきらの《白器 ダイ/台》(2017年)など、いずれも伝統的な素材と技法を新しい発想でこれまでにない斬新な造形へと導き、伝統工芸の潮目を変えたと思われる代表的な作品である。これらはいずれも日本工芸会の中から生まれてきたものだ。会の外からは、丹波の市野雅彦、萩の十三代三輪休雪らの伝統的産地との向き合い方や、現代美術からも高い注目を集める新里明士、見附正康らの躍進が、伝統工芸へと照射するメッセージも合わせて読み解きたいところである。伝統工芸のある未来、その鍵はここにあるのではないかと思う。 (『現代の眼』637号) 註 重要無形文化財の指定並びに保持者及び保持団体の認定の基準(文化財保護委員会告示第五十五号)昭和五十年十一月二十日文部省告示第百五十四号 改正

初代山川孝次《金銀象嵌環付花瓶》
初代山川孝次(1828–1882)《金銀象嵌環付花瓶》1877年頃高さ56.5、幅27.4、奥行19.0cm令和2年度購入撮影:エス・アンド・ティ フォト 紡錘形の中央胴部を残した形の銅製花瓶で、器面全体に如意文、雷文、菱青海波文、変形パルメット文、獣面といったさまざまな文様がちりばめられています。こうした文様の由来は、中国や中央アジア、ヨーロッパに求められ、この作品の図案が、各地の文様を取り混ぜて構成されていることをうかがわせます。 本作には図案が残っています[図1]。この図案が掲載された図案集は、殖産興業を目的に内外の博覧会に出品するため、明治政府が主導し、工芸品の図案を画工に描かせ、それを全国の問屋や工芸家に配布、制作させるという政策において編纂されたものです。なかには工芸家が提案した図案に政府部署の官員が修正を加え、それを画家が筆写したものも含まれるといわれますが、いずれにしても図案と実際の作品が照合できる例は限られており、政府が図案指導を行い、当時の美術工芸品に大きな影響を与えたことを示す例として、貴重な作品です。 図1 明治時代の工芸品図案集『温知図録』に掲載された銅器図案『温知図録』(第2輯 金銀銅鉄七宝器之部7) 東京国立博物館蔵Image: TNM Image Archives 本作で図案は、素地の地金に、文様の形に溝や面を彫り、そこへ金や銀といった地金とは異なる種類の金属を象嵌する彫金技法であらわされています。彫金技法は江戸時代に武具類に用いられ高度に発展していましたが、明治維新により、封建的身分制度が廃止されるなど、社会の仕組みが次々と変わっていくなかで、作る対象そのものが急速に不要なものとなってしまいます。こうした事態に直面し、この時代の工芸家の多くが、海外輸出に活路を見出していきました。本作において、図案から実際の作品を制作した加賀象嵌の名工、初代山川孝次も、まさにこうした変転の時代を生きた工芸家でした。 山川は、金沢の地で市井の人々に人気の作風で評価を得た実力者でした。山川が手がけた刀装具が今日に伝わっています。そのうちのひとつでは、武家に人気のモチーフであった虎が取り上げられており、高彫で立体的にあらわされ、牙を剥く表情や毛並みが繊細かつ生き生きと造形化されています。こうした特徴から、自由な作風で知られた江戸の名工・横谷宗珉(よこやそうみん)にちなんで、山川が「加賀宗珉」(そうみん)の異名をとったという伝聞も頷けます。その力量が認められ、山川は1862(文久2)年に、12代加賀藩主前田斉泰(なりやす)に登用されています。 維新後、山川は、海外のコレクターや資産家向けの高級銅器の製造を目的とし1877(明治10)年に開業した銅器会社に入りました。会社設立当初の職工は50余人ともいわれています。そのなかには、山川をはじめ、藩政時代からの名工とされる平岡忠蔵(ひらおかちゅうぞう)、八代水野源六(みずのげんろく)らが名を連ねていました。江戸時代から培われてきた高い技術を背景に、銅器会社の制作した作品は国内外の博覧会で受賞しています。 図案集の手本を見るような本作に、軽妙さや洒脱さを発揮していた山川の作風を見出すことは困難です。銅器会社では、制作に多くの職工が携わり、山川はそのまとめ役としてディレクター的な役割を担っていたという点も彼の作風が影をひそめた要因となっているのでしょう。本作には銘がありませんが、第1回内国勧業博覧会(1877年)に本作と同じ作品一対が山川孝次作として出品されています。 この後1882(明治15)年、山川は54歳でこの世を去ります。歴史に「もし」はタブーですが、山川がもう少し長生きしていたのなら、変転期を潜り抜け、再び山川らしい個性を活かした新たな作品が評価された時代が到来していたかもしれません。同じ彫金の技でこの時代を生き抜いた加納夏雄が帝室技芸員(日本の戦前期に、優れた美術工芸作家に与えられた栄誉職)に任命されたのは、山川の没後8年後の1890(明治23)年のことでした。個性をひそめ、時代の要請を高いレベルで受けとめ制作された本作に、明治の変転がいかに大きな影響を工芸家たちに及ぼしたかが偲ばれます。 (『現代の眼』637号)
 No image
No image
ウィンター、 アドルフ
 No image
No image


